それは戦前のこと、まだ私も若かったが、どういう訳か丹沢山の魅力にとりつかれて、暇があるとその山中に深く分け入って行った時代があった。
いわゆるスポーツとしての丹沢登山に無中になったのではなくて、史実と伝説の跡を追い求めていたのである。
或る時、私は西丹沢の奥地の渓谷に添って地蔵平という不思議な集落が存在することを遇然知った。
西丹沢の諸水を集めて酒匂川の本流に流れこむ河内川にそって北に遡って行くと、西丹沢の玄関口落合という部落かある。この附近はいわゆる三保三川といわれる、中川、玄倉川、世附川の三川が合流して河内川となるところである。今はこの辺の地形は三保ダム(丹沢ダム)が出来たのですっかり変わったが、昔はここから三川のうち最も西側にある世附川に添って西にすすむと、古い集落の世附、浅瀬などの部落があって、その浅瀬部落のところへ、真北から大又沢という渓流が流れこんでいる。
その大又沢を遡行して行くと、中程でまた法行沢が合流する。この辺は標高七〇〇メートル地点だが、この渓谷いの小さな平地の土中から、縄文土器が発見されたのである。これが物語の発端である。
数人の世附杣人がそれを持って遠く小田原の私の家までやってきて鑑定を求め、そして是非現地を見てほしいというのであった。そこで、三月の末に私はひとりで出かけていった。その頃はまだ世附、浅瀬に自動車の便もなく、大又沢の軌道もないときであったので、もちろん歩いて行ったのである。私の姿を見ると世附の村人達は歓喜して迎えてくれた。
法行沢の発掘は終日続いたが土器の破片一、二をようやく探し当てたくらいで、ほとんど収獲はなく日はすでに西山に傾いた。
私か落胆しているのを見て人々が慰め顔に言うのには。 「この地の更に奥地に地蔵平というところがあって、二十軒ばかりの部落がある。そこには雁丸という武田家の落武者の家があって、古い文書を沢山持っているそうだが、なかなか他人には見せません。だがあなたなら見せてくれるでしょうから、今夜はここに泊まって、明日その家に行ってみませんか」 というのである。それを聞いた私は興味を持ち、 「それでは明日と言わず、すぐ行って見ましょう」 といって、それらの人々の案内で大又沢を更に北に進んだ。歩きながら案内の人々は、 「雁丸さんの家は武田信玄に仕えた有力な家柄であったそうですが、古い書き物が沢山あっても、その家の人もよく解らないとのことで、もちろん部落の人々も見せてもらったことがないから余計にわからないのです。
主人がなかなかの一徹な人で、今まで外部からはいってくる人には決して見せませんが、今日あなたが研究においでになったことは、雁丸家でも承知しているはずですから、話せば解ってくれると思います」 と話してくれた。更に言葉をついで、 「何しろ雁丸さんは頑固な方ですからなあ。うっかりな事を言って気にさわらせたら、どう頼んでも見せてくれませんから、気をつけて下さい」 と言うので、これは大変なことだと思ったが、このような話の中にも、雁丸家が如何にも武田家の落武者らしい風格を持っていることがしのばれて、一層興味を深くしたのである。
地蔵平というところは、大又沢をつめきったところにある盆地状の小平地で、大ツガ、菰釣山(一三四八m)、ブナ沢の頭、城が尾峠(一一九九m)、大界木山(ーニ四七m))、畦が丸(一二九二m)、屏風岩山(一〇五一m)などの1000メートル級の西丹沢の雄峰が西から北、東へと三方を囲んでそびえ立ち、これらの山々から落ちるシキノ沢、白水沢、バケモノ沢、セキノ沢などの小渓流が合して大又沢をつくる所にあった。
その頃の雁丸家は、甲州に抜けようとする急峻な城が尾峠道の登りにかかろうとするところ、部落から少し離れたところに建っており、当時の家は傾きかかった誠に粗末な家であった。
日はすでに暮れかかって、林の黒い陰が、家のあたりの草むらに落ちていたが、当主雁丸七郎氏はすでに私達の来るのを知って、家の前に立っておられた。
夕陽が城が尾峠の彼方に沈みきって、暮色が深くあたりに迫った頃、七郎氏は私か話す武田氏滅亡の悲話に、しんけんに耳を傾けながら、ありし日の祖先を追懐してか、日に焼けた顔に涙が光っているようであった。
突然七郎氏が言った。「先生はいつまで家に泊まっていけるか」 私は「今夜一晩だけご厄介になりたい」と言うと、
「先生は私の家を冷やかしに来たのか。そんなのなら今からすぐ帰ってくれ。私の家を本当に調べてくれるなら、一週間は泊まって行け」 と言うのである。
かくして、私はこの西丹沢の秘境地蔵平に数日を過ごすことになった。
(新名所となった丹沢湖)
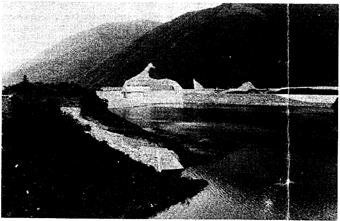
(ニ)雁丸家由緒談義
私と雁丸氏とが屋内で話し込んでいるとき、庭先では妻君がこの突然の珍客を歓待しようとして、しきりに夕餉の仕度を急いでいた。
同家には五、六歳の男の子が一人あって、その子が母の側につきまとって、何か懸命にねたっている様子が見え、そのうちに母親の許しがでたのであろう、大喜びで家の回りを駆け回わるのである。
あまりに嬉しそうなので、私か雁丸氏に聞くと、雁丸氏は、「実はね、私のうちでは毎夜米のめしをたべることがないんだよ。夕食はいつでも干うどんをたべているんだが、今日は先生が泊まるんで、家内が米のめしの仕度をしながら、お前にも食べさせてやるよといったんで喜んでいるんですよ」と言うのである。私は全くびっくりした。
地蔵平というところは、周囲を高山に囲まれた小さな平地だから水田は勿論なし、陸稲もできなければ、稗も粟も作っていない。野菜なども家の囲りに少し種を蒔いている家もあるが、それだってよくは出来はしないのである。
部落全体が完全な山稼人で、木こりか炭焼であったから、その製品がたまると、それを馬の背につけて、大又沢の渓谷を下り山北に出るか、更に世附峠を越えて駿河の小山町に出荷して、それを売った金で食糧品を町で仕入れて山に帰るのである。
従って部落全体が貧しく、主食は粉であった。米のめしは年に何度かの祝日か、客のある時に限られていたのである。
七郎氏の語るところによると、以前は刀槍甲冑の数も沢山あったが、父の代に町方から訪ねてきた男にだまされて、全部失ってしまったという。それ以来、外来者には警戒しているので、この古文書も今まで誰にも見せていないということであった。
そもそも雁丸家は藤原隆家の流れで、もとの本貫地は九州豊後国であるという。 室町時代の中頃、東に移って甲斐の武田氏に従って重臣となり、東山梨
本家は河口湖畔の船津村附近を領して代々小林尾張守を称したが、一族には小林和泉守を称したのもあったらしい。
小林姓を雁丸に改称したのは天正十年(一五八二)の武田氏滅亡の時で、小林尾張守家親が雁丸七郎左衛門と名乗ったのに始まるのであるが、家親は郡内下吉田村に移って浅間神社の御師になった。そして上、下吉田村と福地村との三村を支配していたが、いつの頃か家が衰えて一族は流転し、現在の雁丸家の祖が武田党同僚の後を追って世附山中に入るようになったらしい。
残された雁丸家の資料や、七郎氏の語るところを総合すると、以上のような系譜が明らかになったのであった。
すると七郎氏は、「そう言えば私の祖先の墓が下吉田の水上山月光寺にありまして、「宗賀無明庵了光禅定門 天正十二年辰十二月十一日 小林尾張守」と墓碑に刻されてあるんです。この人が武田家に仕えて活動した偉い人物で、小林家中興と言われているんですよ」 と言うから、私か、「恐らくそれは尾張守家親のことだと思います。武田家滅亡のころに活動し、後に御師雁丸家を興したのですから中興の人というのでしょう」と返答したところ、雁丸氏はいよいよ興奮して、 「ところで私の家の姓ですが、私は普通の戸籍の上では雁丸七郎と申すのですが、この山でも山梨の方へ行っても、小林七郎でよく通るんですよ。二つの姓を甲乙なく用いているんですが、こんなのは世間にはあまり有りませんでしょうなあ」と威張るのである。
(三)雁丸家の古文書
雁丸家の古文書のうち、まず、最も私の目を引いたのは、足利尊氏自筆の軍勢催足状と武田信玄印判の感状とであった。 足利尊氏の軍勢催促状は、建武二年(一三三五)二月の初め、尊氏が京都の戦に敗れて西走し、九州で頚勢をたて直し、翌年の延元元年五月 (建武三年二月二九日延元と改元)に大挙して東上することになるのであるが、その九州で兵を集めたときの書状であった。その中で尊氏は新田義貞を凶徒と呼び、これを抹伐すべきにつき、野上次郎三郎に軍勢を催すように命じているのである。この時尊氏は同文のものを九州の多数の諸豪族に送っており、すでに同種のものが数枚発見されていて「大日本資料」にも一本が所載されているが、雁丸家のものも尊氏花押の真筆に間違いないもので貴重である。 この野上家は豊後国球珠郡の野上邑から興った清原氏系の北九州の豪族であった。この家に関する鎌倉、室町時代の文言が多く残されていて「野上文書」と言われているが、この「野上文書」の一つが雁丸家に所蔵されているというのは、前述したように雁丸家が九州豊後の出身であ
武田信玄の感状もよいもので、川中島合戦のおり、信州水内郡において敵首七個をあげたので、その功労をたたえて属将小林尾張守に短刀一振を与えて賞したものであって、これも珍しいものであった。
(世附川上流を行く)
しかし私の興味を引いたのは「年代古事記」と表書きのある一巻の書物の発見であった。
この書物を、多数の雑然たる古書や、書き付けの中から取り出したときは、書物の表題から例の奈良時代の「古事記」の抜粋写本でもあるかと思い、あまり気にとめていなかったが、中を開いて見ると第一頁に南北朝時代の北朝年号の貴楽という文字が目にとまった。奇異に思ってよく見ると、その時代から戦国の世の天文、永禄の頃までの武田氏を囲んで起きた事件を、年代順を追って記したものであった。この種のものなら有名な「明法寺記」という書物が
「明法寺記」とは、後土御門天皇の文正元年(一四六六)から、正親町天皇の永禄四年(一五六一)までの九六年間の年代記で、甲・駿・越および関東諸国に関する事跡を、武田氏を中心にして書いてある確実性の高い記録であり、甲斐国都留郡木立村妙法寺の僧が代々引き継いで書いたものということになっている。
戦後時代における武田氏の動静について、他の書物や記録にない事実を多く語っているので、同家研究の好資料として知られているものであるから、「年代古事記」を一見しただけで、これは「明法寺記」と同一のものであることがすぐわかった。
しかし、何故「年代古事記」という表題になっているのであろうか。
明法寺に伝来した記録なので、後世「明法寺記」と呼ばれていろいろの伝本ができたが、本来は「年代古事記」と呼ばれていたのではないだろうか。 そんな気がする。
今一つ、元来「明法寺記」は伝来本が多くあって、現今の刊本にも史籍集覧や続群書類従などに採録せられているが、それらの刊本を見ると字句の脱落、伝写の誤りと思われるものが所々におることが知られるので、もしこの「年代古事記」が伝本明法寺記と写伝系統が異なっているとしたら、この書によって従来の伝本の誤りを訂正することが幾分でもできるであろう。
雁丸七郎氏が突然次のようなことをいう。
「その「明法寺記」という書物は、明法寺に伝えられていたのが世に出たので、そのお寺の坊さんが書きついだものと言われるようになったのだろうが、実は私の祖先が書いたものではないでしょうか。
私の家(小林氏)は代々武田氏の祐筆を兼ねていたのです。「年代古事記」というこような名で、そして古い形で私の家に伝わっていることを考えると、祖先が書いたものと思われるのです」と言うのである。
なる程、雁丸家の祖小林家は、武田信玄に仕えて武将というよりは祐筆として文章・記録に活動した家であるので、そのような推定をして見ても悪くはない。
何れにしても、雁丸家所蔵の「年代古事記」は諸刊本の「明法寺記」より語句の筋が通り、誤字を訂正し得ることも少ない。

2,まぼろしの村、地蔵平(下)
「かながわ風土記」(1981年9月50号)より引用しました。
(四)地蔵平秘景
私の最初の地蔵平入りは、雁丸家に数日滞在した後一たん山を下ったが、翌年もまたその翌年も一度は雁九家を訪ねて、数日同家の厄介になるのが年中行事のようになった。そしてその間にも、西丹沢の沢をのぼり、峠を越え、また渓谷から渓谷を探り歩いた。
ある年、地蔵平の南の大又沢の奥にある数軒の炭焼部落の中の一軒に数日足をとめたことがある。
その家はそこでは一番よい家で、松田さんといい、甲州南都留郡から丹沢に入って来たのだという。主人も妻君も四十歳ぐらいで、十六か、十七ぐらいの娘が一人あり、三人で炭を焼いたり、材木の伐採などをして暮らしていた。
初めてその家に宿泊した夜、私は寝床につこうとして便所に立ったが、粗末な家の中にはどこにもそれらしいものが見当たらない。仕方なく家人に気付かれないように外に出て、家の裏手の草叢に行き、息をこらし、音をひそめて用を足した。
何故か、その時、空には星がきらきらとまるで降るように無数に輝いていたのを今でも覚えている。
その翌朝、早く目をさまして起き出したが、丹沢の奥地では五月でもうすら寒くて、主人は炉端にあぐらをかき、しきりに薪をくべていた。だが、細君も娘もあたりには居そうもなく、主人だけがいて、「先生早いんだねえ、もう少し寝ていりやいいのに。しかし俺んところのようなせんべい蒲団じゃ、よくも寝られなかったろうからなあ」 と言って、茶を一杯すすめてくれた。
「顔を洗うのは、林の向こうの谷間でやって来なされ。うちにゃ井戸がないからねえ」と言うので、私は手拭をさげて表に出た。 家の前には美しい樫の林があり、一本の小道がその中を抜けて渓流に降りて行くようになっている。 五月の新緑の林にはモヤが一面に立ちこめて、巨木の黒い幹がかすかに浮かび、二十メートルほど先は、かすんで見えないくらいだった。私はその小道を渓流の音を頼りに進んでいった。
突然五、六メートルの先のモヤの中に人影を見つけ、思わずそこに立ちすくんでしまったのである。それは異様な光景であった。 林のまん中のその小道の両側に、この家の細君と娘とが、そこにかがみこみ、二人とも白い肌を腰のあたりまでまくり上げて用を足しながら、面白そうに話し合っていたのである。 乳白色のモヤが二人の女性のその姿を包みこみ、えもいえぬ美しさでもあった。
しかし私は、見てはならぬものを見てしまった気恥ずかしさで、そこに立ちすくんでしまったが、私のことを気付いているのか否か、二人の女性の姿はそのままでしばらく動かなかった。 巨木の美しく立ち並んだ樫の林の中で、まさに上昇しようとするモヤが、二人の女性の怪しい姿態を消し去ったり浮かび上がらせたりしている。
私は一瞬、神々の時代のことを思い浮かべた。用を終えた細君と娘はおもむろに立ち上がったが、その時、妻君が私を見つけて、 「先生様、お早ようございます。ゆうべはよくおやすみになられましたかなあ」 と頬笑みながら話しかけてきたが別に恥ずかしいという様子なもかった。
しかし娘の方は、さすがにてれて、少し赤くなりながら、だまって下を向き、私の前を通りすぎて、さっさと家の中にはいってしまったのである。
そこで、主人に教えられた小道を急で下り、渓間に出て、郷に入っては郷に従えとつぶやきながら、そこにかがんで存分に用を果たしたのである。そして急に晴々しい気持になった。側には大又沢の渓流が音をたてて走り、小さなしぶきをあちこちで上げていた。これも昔の話になった。
(五)大叉沢の娘
その翌年、私はまた大又沢入りして松田家に宿をとった。夕食がすんだ後で、松田さん夫婦が急にまじめな顔になって「先生に折入っての願いがある」という。それは「自分達夫婦には男の子がなく娘が一粒種である。目に入れても痛くない程可愛いいが、その娘も今年十八になった。
自分達は山稼人の子として生まれ、山に住み、山に育ち、山稼人として一生を終わるのであろうが、これは宿命としてあきらめている。しかし、この文化の時代に娘には生涯をこのような生活ではおくらせたくない。里におろして、世間の風に当たらせ、どんな貧乏な家でもよし、百姓でもよし、人間並の生活のできるところへお嫁にやりたいのである。
ところが娘は生まれ落ちてからこの年まで山奥住居で、里の生活をしたことがないから、今だに汽車や電車にも乗ったことがないし、世間のことを何一つ知らない山猿同然の子である。里に出して奉公させて女の修業をさせようにも、こんな山猿は、軽率にそんなことをさせて、どんな結果になろうとも知れない。男にだまされて傷を負うぐらいが関の山。それが心配で、今日まで炭焼稼業の山奥生活をさせて来たが、娘もいよいよ年ごろになったので、その将来のことを思うと、じっとしておられぬ気持になった。
そこで先生にお願いするのだが、先生の家におあづけするなら、われわれ夫婦も安心できる故、給料など頂かなくてよろしい。女中として使ってもらって、女の身だしなみを教えて頂きたい。そして、どんな家でもよいから、適当と思うところへお嫁にやってほしい。切にお願いする」 ということであった。
私はこの話を聞いて、親のわが子に対する愛情をつくづく心に感じ、 「よろしい。確かに娘さんはあづかった」
しかし山奥育ちのせいか、問えば返事するだけで、自ら人に話しかける方ではなかった。
山を下りた私は家に帰り家内に相談すると、家内も賛成だったので、長男、次男がまだ幼少で、子守兼用の女中が一人いたが、それには暇をやり、大又沢の娘の来る日を家族中で待っていたのである。ところがなかなかやって来なかった。
心境の変化でも来したのかと思っていると、ニカ月程もたって、母親が大きな柳ごうりを背負い、当の娘をつれてやって来た。
私か山を下りるとき、娘は着のみ着のままでよこすように、安月給生活はしているが、着換えぐらいはしてやると切に言い残してきたのに、親の愛情は深いもので、 「着のみ着のままでこいとおっしやって頂きましたが、そうもなりませんので、ちょっとばかり支度をしておりましたので、こんなにおくれて
私達夫婦は後々までこの娘のことを思い出しては、「大又沢の姉や」といって話題にのせたものであり、子供達も今でさえ時々「丹沢の姉ちゃん」といって懐かしがって追憶する。
背丈は大きくなかったが丈夫な、無口だが愛嬌のある娘であった。
さて、私達夫婦はこの大又沢の姉やに対して特別に目をかけ大切にしてやった。
ところが、この娘が町中の賑やかなところに出るのを極端にきらうのである。子供の守をさせておいても、家の中ばかりにいて、外へはほとんど出ようとはしない。町に出ては雑踏の人ごみをきらい、汽車や自動車や電車に乗ることがこわいのである。
娘盛りの十八まで山奥の炭焼生活をしていて里の生活をしたことがないし、汽車や電車に乗って遠くへ行ったこともない。その上に、彼女が山を降りるとき、「お前のような山猿は、世間のことはなにも知らないのだから、町へ出たら余程要心をしないといかん。先生のところでは行儀をよく心得よ。町の人にはだまされないように警戒せよ。子供をつれては乗物に注意せよ。子供にけがでもさせたら大変だ」と、何から何までこんな風に言い聞かされてきたので、娘は極端な自己卑下に落ち込んでしまったのである。そして半年ぐらいするうちに娘は一種の神経衰弱気味となって、やせるのが目につくようになってしまった。
私達がいろいろ心配してたずねて見ても、「何んでもありません」を繰り返していたが、或夜床につく前に、私の妻の前にべたりと座って、「山に帰して下さい」 と言って、ほろほろと涙を流したのである。
それから数日後、私は娘をつれて西丹沢に入り、大又沢の彼女の両親の家へ送りとどけることになった。 娘の両親は涙を流して、私に謝辞をのべ、「山猿の子は、やはり親の住む山の中が一番住みよいのでございましょう」 と言って、何回も我が子の肩をなでていた。
その翌年、私はまた丹沢に入って、ついでに大又沢の家を訪ねて見たら、娘ははち切れるように太って、鼻歌をうたいながら、元気で炭焼小屋で働いていた。
(六)地蔵平の聚落ついに消ゆ
昭和十年(一九三五)を境として、その前後のころは、西丹沢世附奥地の山稼集落の全盛期であって、沢々に面していくつかの集落があって活気を呈している状況は壮観ともいうべきものであった。
私がこれらの集落を歩き回ったのは、これらの集落の全盛期がやや過ぎた頃であったかも知れないが、それでも集落に住む人々の活気のある杣人活動の生活ぶりをつぶさに見ることができた。
初めて地蔵平に行ったころ、大又沢の渓谷を歩いていると、山の奥の、しかも遠くのところから異様な音が腹にしみるように聞こえてくる。木を伐る音かと思うとそうではなく、ハッパをかける音かと思うとそうでもないらしい。
ごーん、ごーんと、一しきり間断なく妙に中にこもったような音が、山谷にこだまして、恐ろしいような響きであった。
土地の人に聞いて見ると、 「あれは神社の祭礼などに使う大太鼓の胴を作っているんですよ」 といっていた。
大太鼓の胴は、大ケヤキの木を探して作るのだそうだが、もう西丹沢でもこれを作るような大木は、よほど奥地にはいらないと無いということで、それを見付け出すと、数個に切って、主幹の間にその場で芯を抜く作業をつづけるのだそうだ。その作業音が谷々に響きわたるのである。
出来上がった太鼓の胴は、馬の背に積まれて小山町まで運ばれて商人に渡すのだそうだ。それが東京浅草の太鼓屋に持ってゆかれ、そこで皮を張られて仕上げられ、全国の需要者に売られるのだと言っていた。太鼓の胴作り、これがよい稼ぎであると言っていたが、こんなところに変わった職業が行われているものだと驚いた。 また、ここには古くから地蔵尊が祀られてあって、地蔵尊の祭礼は婦人達のみでやる習慣があるということであるが、地蔵平の地名はここから起きたのである。
ここから大又沢を下らずに、登ると屏風岩山と権現山との鞍部の峠を二本杉峠(七三四メートル)という。この峠を東南に越えて中川の流れに沿った上ノ原部落に出る道は、いまは淋しい草道になってしまっているが、昔は盛んに利用された古道であった。地蔵平からまっすぐに北へ城ヶ尾峠に登って、それより「さがせ道」というのを通って、道志川の流れに沿う善ノ木に出る古道に連結すると、山中湖−道志川−城尾峠−地蔵平−二本杉峠−中川と結ぶ甲相古道が考えられ、地蔵平はその中継集落として、古い集落であったことが知られるのである。 地蔵平の盛時には、大又沢と両集落を合わせて四十軒ぐらいあって、三保小学校の大又沢分校があり、男の先生がひとりで寄合小屋のようなところで教えていた。
新学期になると、その先生が児童の教科書や、紙、鉛筆、ノートなどの希望をつのって、その覚書を懐に入れ、大きなリュックサックを背負って大又沢を下り、山を出て行ったのである。小山町へ行くのか、山北町へ行くのか、小田原市へ行くのか知らないが、二、三日すると、リュックサックからあふれる程に買い入れた品物を背負った先生が帰ってきて、子供達に学用品を分配し、ついでに買ってきた町場の菓子などを与えて、子供達をよろこばせていた。
世附川の本流を大又沢にはいらずに、本流を更に西にさかのぼって行くと、次第に甲州に近くなり、山も深くなる。広河原というところで、西の方から来る土ノ沢と、北から来る水ノ木沢とに分かれる。水ノ木沢を更にのぼって行けば、大棚沢、金山沢、織戸沢の渓流が流れこんでくる。この辺一帯は、いわゆる「丹沢世伝御料地」と言われたところで、当時は全く西丹沢第一の深山秘境であった。 水ノ木沢と織戸沢との合流点に世附休泊所が設けられてあった。休泊所と少し離れたところに炭焼場があって、数家族が仕事に従っていた。
私はその水の木沢を詰めて行った。すると、菰釣山から流れ出るのが水ノ木沢の本流で、その西にある石保土山から流れるのが金山沢であった。それが水ノ木沢に合流するところにも、二軒の炭焼家族が住んでいた。
ここから金山沢の方を詰めて行くと、モミノ木沢が合流してくるところに、遠くから見ても数条の煙があかっているのが見えた。近付いて見ると、谷の両側から迫った狭い河原に沿って、沢山の炭焼窯が立ちならび、その間に掘立小屋のような住居が点々とあって、男女が沢山入り乱れて賑かに右往左往して炭を焼いていた。私はそこの活気にあふれる空気に圧倒された
しかし、更に驚いたのは金山沢の水源に沿った荒れた道を分けのぼって行くと、それは山中湖に向かって行く山伏峠へ出る古道であるが、その水源地のサカサオーイという小平地に一家族の木こりの家があって、その家の主人の方も、
「旦那、こんなところへ何しに来ましたかね」 と驚いていた。
戦後急激に発達した登山熱で、近頃はこの道を歩く人も多少あるようだが、その頃はあまり普通の人は入らなかったようである。
その頃の世附山稼ぎの壮観は、この感激を今の人々に話しても本当にはしないであろう。
土ノ沢にも大棚沢にも数軒づつの炭焼家族が住んでいて、窯の煙をあげていた。
さて、これらもすべて古い話になった。昭和初期の話であるからである。
太平洋戦争が終わってから、私も身辺多忙を極めるようになり、自然と丹沢の奥地を訪ねることも間遠になっていった。
その後、人から聞いたところによると、浅瀬から大又沢の渓谷に沿って軌道ができ、地蔵平に行くのも便利になったということであるので、もう一度行って見たいと思っているうちに、いつしか、そのまま年月が過ぎてしまったのである。 ある年、三保小学校の本校に講演をたのまれて行ったら、その席に居
それに、当時きれいであったあの細君も、すでに世を去ってしまったという。
そしてまた数年、雁丸氏が軌道で不幸な死を遂げられたということもほのかに聞いた。
思えば、あの私達夫婦が「大又沢の姉や」と呼び、子達が「丹沢の姉ちゃん」と呼んだあの娘は、今はどこに暮らしているのであろうか。どのような人の妻になり、誰の母親になっているのであろうか。そんなことを考えて、この人のことを尋ねてみが、とうとうわからなかった。
そのうち、テレビかラジオで大又沢の三保学校分校が、先生一人、生徒一人になって、いよいよ廃校になるというのを聞いた。
世附杣人集落にも時勢の波が押しよせて、変転また変転して、どの杣人集落も次々と姿を消していった。
そして、近頃また人の話に、「今は地蔵平も大又沢も金山沢にも、もう一軒の家もありません。地蔵平はむかしこんなところに多数の人々が住んでいたのか、と思うような荒地となってしまっています」と、行って来た人が話してくれた。
奥世附の山作の盛時の壮観は、私の瞼の裏に残るのみのものとなってしまった。
奥世附のなつかしの地蔵平集落は遂に永遠に消え去ってしまったのである。ああ、幻の村、地蔵平よ。
3、「城が尾峠より菰釣山へ」 紀行文 水田健之輔
山と渓谷131 創刊20周年記念特大号 昭和25年4月1日発行
昔の大又部落(地蔵平)の様子が書かれています。
南風が吹き出し、畠の青麦が熟れ出すと心も浮きうきとして、山が恋しくなる。千米内外の低山が懐しくなり、新緑の山旅を試みることにした。
白羽の矢を立てたのが丹沢山塊中不遇の山である菰釣山だ。小田急の新松田駅に下車して、神縄行のバスに乗る。西丹沢への山入りはさすがに少いとみえて登山者は私達一行二人だけである。
河内川の出合峰附近では桜が満開、美事なので集客は窓から首を出して褒めた。神繩でバスを捨てて河内川に沿うて歩けば、樹々は若芽をひろげ始め、小鳥も待ちかねていたかのように声高らかに囀る。
落合部落で、左折し世附川下流の右岸に沿って世附部落に出る。背後には権現山の?峯がおし迫り、うらびれた草屋根が點在している。
この邉りの民家は甲州系統のようで、所謂兜造りも見受けらる。山畠の桑樹も新芽を吹いて麗わしい。
世附部落へ出たが、まだ一時半であったので、日長の春であるから今夜の宿泊地蔵平には充分時間がある。そこでこの部落の民家を研究しようと、石原博士と二人で、山本信吉さんの家を訪れた。
地蔵平に着いたのは四時過ぎであった。今日は部落の観桜會とて、どこの家へ行っても皆んな不在だ。ながい冬籠りから解放され、山の人々が、男も女も、子供も年寄もみんな満開の櫻の木の下で、大宴會をするのも快よい山の春風景である。
この部落の氏神係の野崎巌さんの家(岡澤重夫さんの本「誰も知らいない丹沢」のコラムにある「地蔵平の女の子」に登場する女の子の家)」・・・YK記)に泊めて貰う。この山奥の部落は昔から相甲をつなぐ要路であったので、戦國時代既に武田派が利用していた。徳川時代には関所を嫌って駿河の小山町から世附川、大又沢を遡って地蔵平を経て城が尾峠をこえて甲州道志村より甲府へ無手形で通行出来たのが、この裏山路であった。城が尾峠と云えば昔はこの峠をサガセ峠と呼んでいたようである。即ち「風土記」によると、城が尾峠、中川村、四圓總テシ山ナリ(中略)西北ノ方甲州界二城ケ尾ト云エルアリ、信玄屋鋪トモ、信玄平トモ唱フ、(中略)甲斐國志ニ甲州道山村ノ山中ヲ経テ中川村ニ至ル間道ヲサガセ古道ト唱ウ。 又一説には城が見とも云われる。これは信玄屋鋪より考えれば、武田信玄が小田原の北條を攻略する際、ここに陣地を張ったことを意味しよう。即ち城の見える城が尾山の地鮎を城が見と呼称したのを、後日城が尾に轉説したのではないかとも言われる。
東京方面では櫻は散って、既に葉櫻になつているものの、この地蔵平は、今、丁度満開の見頃である。四月の末だが、夜間は春寒峭料で、なお炬燵が欲しい位だ。併し、もう炬燵は使つていない。炬燵と云えば爐を思い出すが、爐を囲んで純情な山の人達と邪気のない話をするのは愉快なことだ。
この寂境に宵闇が泊ると、やがて権現山の方面に四月の満月が昇って、黒い山々は月光に照され、流水の麗わしさと俟つて一幅の名書でも見る墨絵の妙趣がぽっかりと春宥に浮かび出てくる。
バケモノ沢の流れを渡って、植林に入ると「右山径、左城が尾峠を径て道志村」の指標に徒って左の登路をとる。
薄暗い檜林を通抜け、賑かな鶯の朗音を聴きながら、緩い林道を登ると、三十分許りで樹々の新芽と山吹の花が萌えるように咲いている信玄平に出た。特有の路網線を見送って、なおも登ると二十分程で城が尾峠に出た。
私達は南方へ尾根を辿って菰釣山に向う。峠より踏跡を追うが城が尾山よりは踏跡は全く不明になり、中の丸の間までは雑木の藪潜りだ、中の丸よりはクマ笹の藪漕ぎとなる。盗伐越場の登り辺りから、栂、山毛樺の喬樹が亭々と昔その儘の様相で現われてくる。これが丹沢の至賓であり美衣であろう。
この大幽林の中を駒鳥の明るい囀りが沢山の静寂を破っでいる。藪漕ぎの苦闘心忘れ、美しい林相に陶酔しながら掬の丸の頂峯に立つ。
燦として輝く明朗な姿の芙蓉の霊峰を真正面に、右手には御正体山がその東面に二ヵ所の大崩落を生々しく現わして聳ち、左方には鉄砲木の頭より三國山、明神山、湯船山と漸く低く蜿蜒とのびている。また南方には矢倉、金時、駒が嶽の箱根連峯が望まれ、ここの展望も捨て難い。
菰釣山(一三四八・ニ米)は、一名雲吊山とも云う。岩崎京二郎氏によると、四時山頂は雲霧に蔽われ勝ちであるというが、私達は天候に恵まれ展望を恣にした。またこの山名については加藤秀夫氏によると菰で出来た小屋が頂上にあろからだと云う奇説もあるが、自分のきいた所によれば、昔甲州側と相洲側とで國境争いをした時、即ち菰を釣して標としたと論じているが、その一半は肯定されよう。又武田久吉博士によると菰釣しの名は相州の名で、平野では大丸尾と呼ぶそうだが、道志では掬の丸の稱を以て呼ぶらしい(山岳1巻第二号)。
三角點からクマ笹をかき分けて南下すると、所々に大木が聳えている。
約三十分で大ダルミに出た。前面には大ツガが行方を阻んでいる。右のカラ沢を下る。所謂ダルミ沢で、勿論踏跡などない。少し降ると一〇米餘の棚の上に出這入っていて二〇米許りの二段の棚が現われる。この渓谷は降るにつれ美観を呈しいてくる。
やがて右岸に山腹を捲ぐ林道を発見し、これを辿ると金山沢との合流點に出る。丸木橋を渡って對岸に移ると材木搬出の軌道の終點に当たる小屋の前に出た。ここから十分許りで水の木に着く。
この邉りの景観は素晴しい。山は新緑に包まれ圓味を帯び、それが群がる美林を透して一條の瀧が水量も豊かに落下しているさまは、真に大雅堂の絵を見るように津々たる興味ぶ湧いて来る。この瀧は大棚である。軌道を踏んで下ると、左の脚下は本谷川が流れ、美岩を洗う渓水はみるからに清気骨に徹して心身を淨化する。
左に曾遊の不老山を見ながら溌剌たる春山に別れを告げ、柳島部落に降れば、青々と波うつ麦畠の上に春風が流れでいた。小山町では式場に向う花嫁が仲人や付添の人々に守られてはずかしそうに町中を歩いている姿も麗しく春宵の感を一としほ深められた。